原田広美

夏目漱石(1867~1916)は、イギリスに官費留学する前には、松山中学や熊本五高で英語教師をした。熊本五高で教えたのは、鏡子と一緒になった新婚時代だ。少年時には、講談・落語や漢詩を好んだ漱石は、英文学を志してからはシェイクスピアが好きで、熊本五高時代には、朝早く学校に行き、特別授業としてシェイクスピアを講義した。
その後、漱石がシェイクスピアを論じたのは、ロンドンから帰国後の、〈神経衰弱〉が最も酷かった頃のことだ。ロンドンで、正岡子規から「もう(死期が迫ったので)生きては会えない」という意の葉書を受けた時から、漱石は一人で部屋に閉じこもって英文学を独学し、小さな字を連ねたノートを何冊も作った。
私が思うに、ゆくゆく作家として立った漱石には、若い頃から内在的には「文学(創作)への夢」があった。その傍らで、結核という病があった子規は、早くからその道に邁進したので、漱石にとって子規は、大変に頼りになる輝かしい存在だったと思われる。
結局は、漱石の〈大学院時代の学友・小屋保治〉の妻となった〈閨秀作家の大塚楠緒子〉への失恋を経ての〈都落ち〉だったのか~とも言われつつ、愛媛の松山中学に英語教師として赴任した際にも、漱石は、子規が主宰する俳誌「ホトトギス」を大切に持参した。
一方、病床に伏す以前の子規は、俳句革新運動にいそしむのみならず、新聞「日本」の従軍記者として、日清戦争の最中には大陸にも渡った。学生時代から結核の喀血があった子規は、大陸からの帰途でも喀血し、自ら(子規)の生まれ故郷の松山の中学教師になっていた漱石の二階建ての借家で、一夏を過ごして静養した。
そこでも子規は句会を開き、高浜虚子や河東碧梧桐も出入りしたが、後に漱石の妻となる〈鏡子の見合い写真〉が送られてきたのも、この時である。
〈鏡子との見合い〉に子規は賛成し、やがて先に帰京した子規は、年末に松山から東京に戻る口下手の漱石を思いやり、〈見合いのお膳立て〉にも尽力した。漱石は、新婚時代には熊本から「ホトトギス」に俳句を寄稿し、その後の英国への官費留学時代には、ロンドンから〈倫敦通信〉を「ホトトギス」に書き送った。
「自らの命がすでに尽きそうだ」という子規からの知らせに、漱石は「内在的な文学への夢」を埋没させざるを得ず、本当はあまり好きではなかった「英文学論」をいよいよ「せねばならぬ」という所へ追い詰められたようである。
そもそも漱石が英文学を専攻したのは、少年時に愛好した落語や漢文に別れを告げ、長兄の「文明開化の世の中に従え」というアドバイスを生かしてのことだった。
子規を失いゆく悲しみの中、書物を大量に買い込むゆえの、貧しいロンドンでの留学生活で、「せねばならぬ」の英文学研究に集中し過ぎた結果、深刻な〈神経衰弱〉を発症させてしまったのが、この時の漱石であったと思われる。
人は、本来の「内在する夢」を失い、「せねばならぬ」所に追い詰められた時に、神経や精神を病むというのが、私の持論である。

『ハムレット』の話に行き着かず、周り道をしているが、そのついでに書いてしまうと、―本来の「内在する夢」を失い、「せねばならぬ」所に追い詰められた時に、神経や精神を病む―これを避けるのは漱石のみならず、現代においても、現実的にはやはり難しいこともあると感じられる。
たとえば父親の職業や専門が〇○で、「男の子が生まれたから、きっと〇○に進むのがよかろう」などと父母が思って育てるうちに、抑圧的な関係や要素が家族内にあったりすると、その影響で本人までが抑圧的になり、自らの適性を感受・発揮する間もなく「(適正はないのに)〇○へ進みたい」などと、思い込んでしまったりする。
そして結局はそのうちに、深い喜びを伴わない「せねばならぬ」に追い詰められ、精神を病んでしまうこともある。これには逆のパターンもあって、親が大変な苦労をした結果、「その苦労だけは子供にさせたくない」と考えて、「自分とは別の〇○」をさせようと試みる。
だが「カエルの子はカエル」で、親の生き方とは別物の「〇○」がよく分からず、親が苦心の末に敷いてくれたレールに乗りそこなうことがある。その結果、自分を脱落者だと感じて責めたり、また進路の変更先を見つけるのも難しくて、心を病んでしまうこともある。
本当に人が、自らの進路を見つけるのは大変なことだと思う。自分が喜べるもの、楽しいもの、愛せるものがある方向へゆくことがコツだと思うが、すべての感情(怒り・悲しみ・楽しさ・喜び..etc)が一からげになって埋もれてしまい、自分が好きなもの、楽しめるもの、喜べるものを感じとるのも苦手になっていることもある。
・
話がすっかり飛んでしまったが、ロンドンで煮詰まった漱石は、周囲から東京に「夏目狂せり」の電報が打たれたこともあり、滞在予定の最後を打ち切って早々に帰国した。だが漱石は、その「せねばならぬ」の英文学論を、今度は母校の帝大(今の東京大学)で教えなければならなくなった。
当時は、漱石の将来に〈作家〉という文字はなく、「英文学者になる」との思いで、ロンドンにいた頃から、学友だった者達に就職先斡旋の依頼もしていた。その結果というべきなのだろう、学生達に人気があったラッカディオ・ハーンの教職が解かれて、その後釜として漱石が教壇に立つことになったのだ。
人気があったハーンの後を継いだ漱石の講義は面白くなかったので、学生達から不評を買い、漱石は苦しい所に追い詰められた。だが、それは喜びのない「せねばならぬ」の精神で、個人研究した漱石の「英文学論」に対する的を射た評価ではなかったか。
そして、やはり英国留学の末期以降の〈神経衰弱〉は治まらず、どうにもこうにもならなくなった後、夏休みに妻・鏡子を実家に追いやり、久しぶりに詩作にふけった挙句に、秋からは英文学論を打ち切り、シェイクスピアを論ずる講義に切り替えることを決意した。
シェイクスピアは、近代文学よりも前の時代のものであり、講談や落語という町人文化で育った漱石には、やはり相性がよかったのかもしれない。それに留学以前の高校教師時代から論じていただけあって、英国に留学しても大学には通わなかった漱石だが、シェイクスピアについては、ウィリアム・クレイグに師事して学んだ。
そして秋からは、好きで自信もあったシェイクスピアを帝大でも論じ始めた漱石は、今度は学生達からも大いに受け入れられ、「文科は、夏目先生一人でもっている」と言われるほどになり、新聞記者が取材に来るに至った。そして、その自信を取り戻した年末に、編集が高浜虚子に移っていた「ホトトギス」に『吾輩は猫である』を発表し、作家人生のスタートを切るに至ったのだった。
ここまでの話は、「人は、自らの〈夢〉を遠ざけて生きる時、人生に追い詰められ、自らの〈夢〉を生きる時、困難な中にも喜びをもって、人生を歩めるものである。」(⇦🌸原田広美 著『漱石の〈夢とトラウマ〉』新曜社 https://amzn.to/3Df2KTL より、引用)という話でもあった。

ここから先は、ようやく本題の『ハムレット/オフィーリア』に移りたい。
ここまでには、漱石とシェイクスピア(1564~1616)の関係の話だった。ちなみに漱石は、この文章冒頭のミレー作『オフィーリア』の絵が好きだった。留学中に、ロンドンのテート・ギャラリーで見たのである。
ミレーは「ラファエル前派」に分類される画家で、わりあいに大衆的な浪漫主義である。さすがに町人の家系出身の、漱石らしい好みとも言えるのではないか。だが漱石のシェイクスピア論は、私の知る限り、残されていない。だから以下は、私自身の論であることを断っておこう。
まずは『ハムレット』の恋人が、けなげで無垢なオフィーリアである。しかし、けなげならそれでいいのか? という方向にこの文章は、進むことになるだろう。冒頭の絵にあるように、オフィーリアは入水して自害を果たす。
なぜなら愛するハムレットから「尼寺へ行け、」と突然に言いわたされ、その上に人違いの事故的な要素が絡んだとは言え、やはり愛する父親がハムレットの剣によって殺害されてしまったという、絶望的なショックのためだろう。キリスト教圏では、自害は神の教えに逆らう行為なので、オフィーリアは墓に葬られることも叶わなかった。
次に掲げる写真は、1972年初版(2007年84刷)の新潮文庫『ハムレット』の口絵として掲載された『ハムレット』の上演写真からの引用(部分)で、私などは子供の頃から『ハムレット』と言えばこの写真を見ていたような気がする。写真の下には、(オールド・ヴィック劇団公演、1953年~4年)と解説が付いている。かなり、古い写真だ。

「ハムレットは狂気を演じている」という説もあるが、この写真からは〈ハムレットのドス黒い狂気〉が、そのまま伝わって来るような怖さがある。愛するオフィーリアの腕を無造作につかみ、不敵な笑いを浮かべたような表情で、「さ、行け、尼寺へ」(福田恒存 訳)というセリフを吐く。
父王を腹黒い叔父に殺され、その叔父と再婚した母親に裏切られた思いの王子ハムレットは、狂気に襲われたということなのだろう。あるいは、そうした狂気を演じているというのだろうか。兄を殺して王位に立つ叔父であれば、ハムレットも明日は我が身と(父親と同様に、叔父の毒牙にかかる可能性を)考えたとしても無理はない。そもそも妃であった母親が叔父と再婚しなければ、ハムレットが新王になるはずではなかったのか。
劇中では表立って語られなかったものの、おそらくハムレットにとって重要だったのは、オフィーリアの〈父・兄〉と〈新王〉の関係性、そして〈オフィーリア〉と〈父・兄〉の関係性だったのではないかと思われる。
つまり、かつてハムレットの父親(殺害された元の王)のよき下僕であったオフィーリアの〈父と兄〉は、その元の王に対する従順な忠誠心を、元の王を殺害したであろう〈新王〉に対して受け継いでしまっている。日本流に言えば、常に「お上(かみ)」に対して従順な〈保守的態度〉の持ち主だと言わざるを得ない。
これを言い換えれば、上が挿(す)げ替えられたので「今度は〈新王〉にお仕えします」ということである。これでは〈叔父に対する復讐〉に燃えるハムレットの役に立たないばかりか、オフィーリアの〈父と兄〉は叔父〈新王〉の側の人間なので、ハムレットの敵陣という構図になってしまう。
それに輪をかけて、けなげで無垢なオフィーリアは、いつだって「愛するお父様、愛するお兄様」という立場をとる娘である。これではハムレットの力になれるはずもない。ハムレット自身、亡き父の亡霊から〈ことの真実〉を知らされたばかりの所から話はスタートするのだから、時間経過による各々の理解の様は少々複雑だが、ハムレットの狂気、特にオフィーリアに対する狂気の言葉の意味は、ここにあると見るべきだろう。
このように〈異性への愛〉と、〈親子の(愛)情〉は、相容れないことがあり、やはりある意味では〈親離れ〉が、〈異性への愛〉には不可欠になる部分がある、ということでもあるだろう。オフィーリアも、「愛するお父様、愛するお兄様」と唱えているだけでは、世を渡り切れなかった、〈愛する異性〉と結ばれ得なかった、と見るべきなのではないか。
それでも考えて見ればハムレットの「尼寺へ行け」という言葉には、「あなたきは、他の男のものにならないでほしい」という、気持ちが感じられなくもない。その後、ハムレットが、それがオフィーリアの父とは知らず、幕(カーテン)の後ろに隠れていた所を敵方の盗み聞きかと思い、剣で刺殺してしまう。
それは不幸な偶然でもあったが、やはり〈新王〉に操を立てる立場を選んだがゆえに、オフィーリアの父は、ハムレットに刺し殺されるという運命に導かれた、とも言えるのだろう。
また自分が愛していたはずのハムレットの「尼寺へ行け」という言葉に、オフィーリアが従わなかったことも、気にかかる。そんな言葉に従わなくとも、別の道をしたたかに生き通せたのならそれもいいが、自死を選んだのでは、浮かばれなかった(それで川に浮かぶことになってしまったのだろうか、これでは悲しいばかりである)。
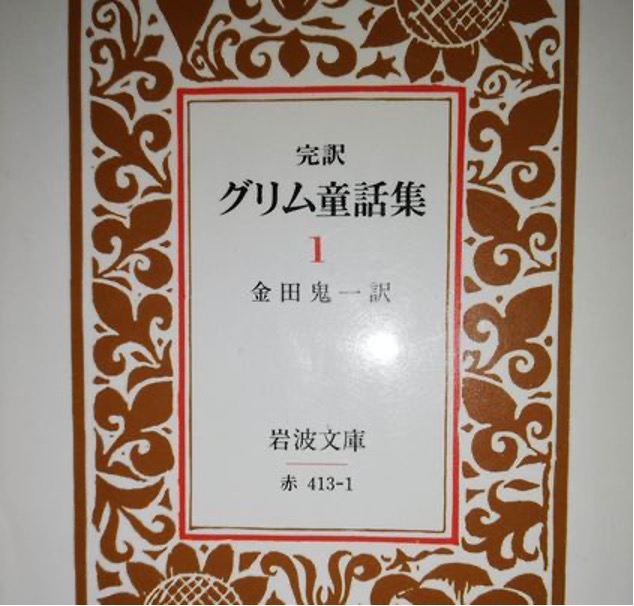
ここからは、グリム童話⎯蛙の王様様、あるいは鉄のハインリッヒ』の話になる。とは言え、『ハムレット/オフィーリア』との関連もあるので、ここに書いている。どのように、この2つの物語が関連するのかについては、読み続けるうちに了解していただけるだろう。
グリム童話は、グリム兄弟(兄:1785~1863/弟:1786~1859)が、ドイツの民間の言い伝えを集めて編纂したものだが、その中でも『蛙の王様、あるいは鉄のハインリッヒ』は、その〈一巻め〉の〈第一話〉であったのをご存知だろうか。
これが最初の話に選ばれた理由を私は知らないが、これは多分にいい話であると感じている。最後に王女様と、蛙から人間の姿に戻った王子が結婚するという、めでたい話だからいい、ということもモチロンある。しかし実は、その後にも尾ひれ的な話があり、それもとてもいい内容なので、後ほど紹介して行こう。
しかも、蛙が王子に戻ることができた経緯も、べらぼうに面白い。
王女様は、お父様の言いつけを無視して、同時に蛙との約束も破って、「こんな汚い蛙と同じベッドで眠るなんていや!!!」と、蛙を壁に投げつけたために、蛙は魔法が溶けて人間の王子に戻ることができたのだ。
庭で遊ぶ王女様の金の毬(まり)が、いつもとは違い、池の中に落ちてしまった所から、この話は始まる。そして、蛙は「お友達になって、一緒にご飯を食べたり、眠ったりしてくれたら、その毬を拾って来てあげる」と言った。その約束をしたはずの王女様なのに、実は初めから約束を守る気はなく、挙句の果てには蛙を寝室の壁に投げつけてしまう。
ここには、『ハムレット』のオフィーリアとは全く別の女性像が現れている。お父様の言いつけをすっかり無視して、幸せを手にした娘が、このお話の王女様だ。そして結局、その娘の幸せな結婚は、父親である王様にとってもめでたく嬉しいことになったに違いない。お父様の言いつけを守らない娘が、幸せを手にして、お父様をも幸せにしたという話なのだ。
やはり『ハムレット』と比較して、こちらこそが生きるために役立つ話、生きるためのエネルギーを補給できる話ではないだろうか。だからこそ伝承されたのではないだろうか。
・
20代の半ば過ぎ、その頃に高校教師をしながら住んでいた淵野辺(神奈川県の相模原市)から、毎週何曜日だったのか、高田馬場(東京都新宿区)にあった「東京ゲシュタルト研究所」まで夕方に仕事の後から通い、所長のリッキー・リビングストンに、ゲシュタルト療法ベースの〈夢とアートのセラピー〉を学んだ時に、この童話を扱った。
物語療法と言えばよいだろうか、この童話を誰かが朗読して、印象に残った場面をクレヨン画にする。そして、その絵の内容や、描いた今の気持ちをシェアしたりした後で、絵の中どこか一部分(モノやヒトなど)を選んで、自分がそれになって感じ、語り、演じるという〈ロールプレイ〉をする。
これは実際にやってみないと体験的な理解はできないものだが、案外自分でも驚く発見があったりするもので、そこから自分の無意識を癒したり解放する糸口になったりするのだ。この時に私が選んだ場面は、実はさきほど書いた粗筋の後に続く場面だった。
どういう場面かと言うと、題名の『蛙の王様、あるいは鉄のハインリッヒ』にある〈ハインリッヒ〉が登場する場面なのだ。
少しここに引用すると、「忠臣ハインリッヒは、殿さま(ママ)が蛙にされてしまったときには、すっかりしょげかえって、胸のまわりに鉄のたがを三本はめてもらいましたが、それは、悲しみのあまり胸が破裂するといけないからでした」と、ある。
ここは、さすがに「忠臣ハインリッヒ」なのであって、『ハムレット』のオフィーリアの〈父・兄〉とは、別の態度であると言えよう。自分が仕えている対象の〈幸・不幸〉と、自らの立場を共にしている。こちらは童話(おとぎ話)で、オフィーリアの〈父・兄〉の対処法の方が、要は現実的なのだと言えるのかもしれないが。
ハインリッヒに戻ると、王子様が人間に戻ることができた翌朝、「白馬八頭立ての馬車がいちだい(ママ)、お城へかけつけて」来た。その馬車の前に〈王子と王女〉を乗せたハインリッヒは、2人の後ろに立ち乗りをして、王子の国へ2人を連れ帰る。その途中で、「何かが破裂したような、ぱちーんという音」が聞える。それは、ハインリッヒの胸のたがが、歓びのあまりに弾け飛ぶ音だった。
何と言う、いい話なのだろうと思う。
私がリッキーのワークでロールプレイをしたのは、このハインリッヒだった。当時は、自身の自己解放に最も関心を寄せていたので、この〈胸のたがが外れて飛び散るイメージ〉が、特に印象的に感じられたのだと思う。
この話を〈父親の言いつけに背いた娘の結婚〉ととらえると、最近で思うのは眞子さんのことだ。20代は高校の国語教師で、勤務して働く女性だった私は、雅子様(および愛子様)に親近感が強く、初めての拙著だった『やさしさの夢療法』https://amzn.to/3XWtY9B にも、雅子様の夢のことが書いてある。
眞子さんの結婚は成立までも難しく、これからも決して容易い道ではないとも感じつつ(そもそも皇室から一般に嫁いだ女性の結婚は、すべて容易くはなかろうが)、お父様の意に反した結婚をして頑張っているのだから(お父様自身も、皇室にいるのが本来は窮屈だと感じる所もおありになるような方だと思う)、何とか幸せをキープして、お父様のお気持ちも幸せなものにしてさし上げてほしいと願う。
(最近の私は、こう感じるようになりました)
……………………………………………………………………………………………………….
*番外お知らせ編*3月23日まで~毎(木)19:00~21:00で特別【無料】のZoomプレ「アートセラピー実験工房」を開いています。*また2月には2月7日から毎(火)13:00~15:00で4回限定で同じ内容の特別【無料】講座を開きます。どなたでも、ご参加できます。
*詳しくは、こちらをご覧ください➡https://bit.ly/3HNL5Fs (全日程の内容説明は同じです)

