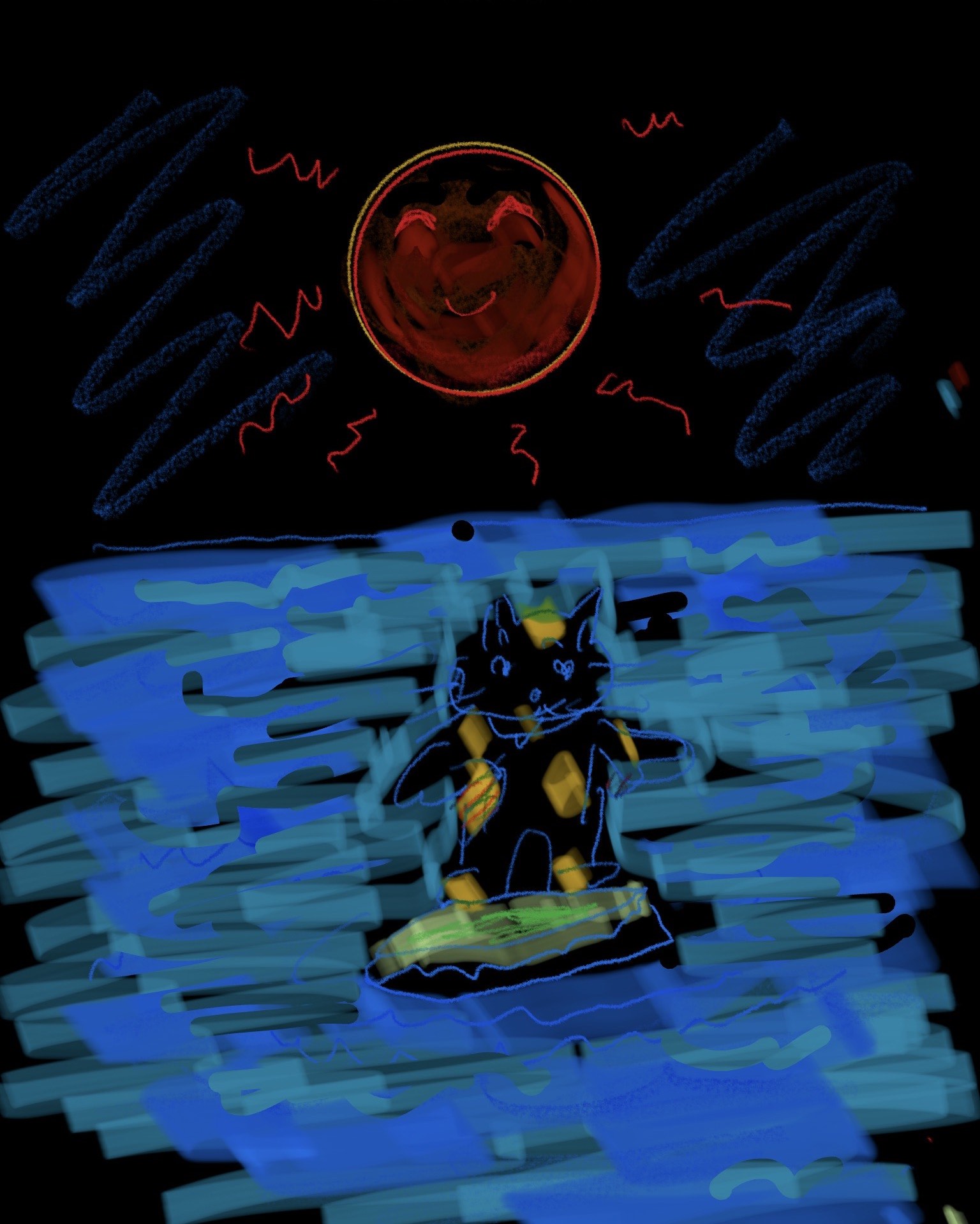田中義之
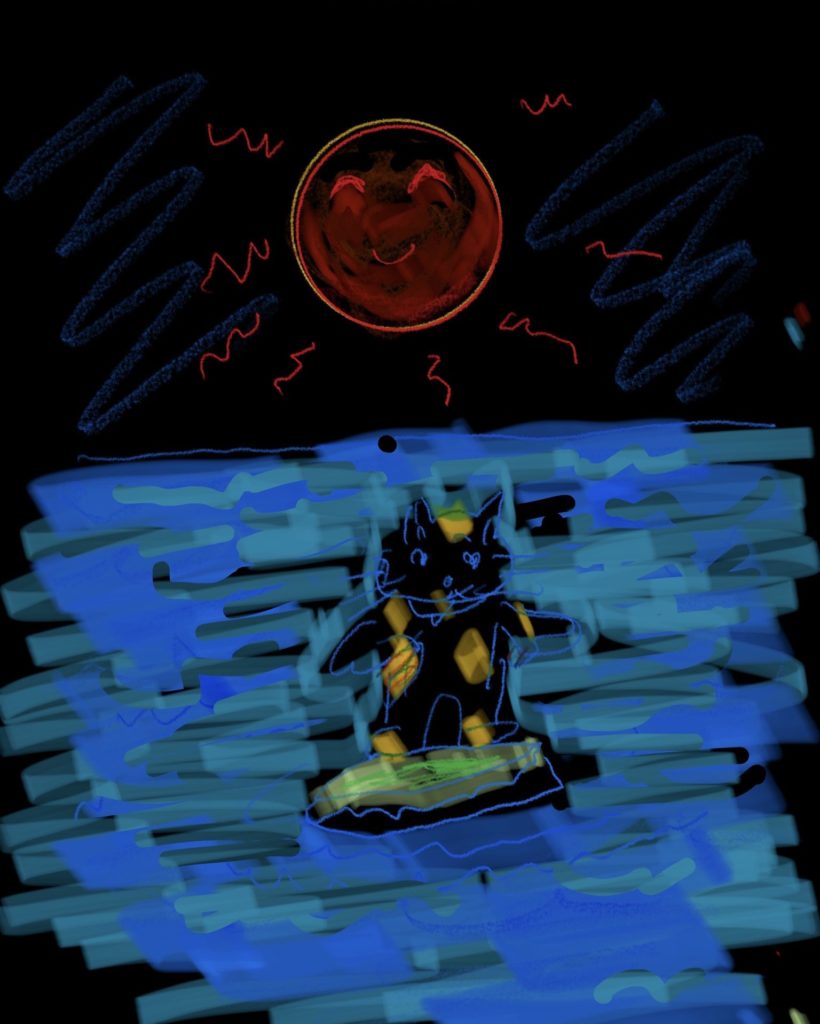
『孤高の豚』って云う短編小説を書いたことがある。主語は、三人称複数。ある独裁国家の元首の存亡(実は安泰) を、民衆側から描いた物で、多分にガルシア・マルケスの『族長の秋』の影響がある。
「『孤高の豚』と彼らは呼んだ。それが、蔑称なのか尊称なのか、彼らの与り知らない事だ。」って云う、冒頭の一文があって。元首が、本当に、豚なのか人間なのかは分からなくなるような描写をしていく。地図にも、載っていない小国家では、レアアースで、莫大な富をなしている。インターネットも、SNSもこの国では、存在しない。
鎖国状態で、大統領執務室に、たった一台、端末があり、外とは、それでしか繋がっていない。
カーニバルを迎える二週間前から、物語は始まる。秘密警察の目をかいくぐって、「革命」そんな言葉はこの国では存在しないが、とある衝動での主人公たち三人の奮闘が始まる。「孤高の豚」と呼ぶ、ある雑誌の出版を、カーニバル当日迄に間に合わせることになる。たった千部の小雑誌である。期間中、飛ぶように売れ、増刷が繰り返される。内容は他愛もない、冗談とも揶揄ともつかないおとなしい物であったが、けして活字化してはいけない「孤高の豚」という単語が出ている。民衆は、それがどういう意味か、なんと読むかも、判読できないが、なんとなく気になる。そして、カーニバルの後半まで、政府・秘密警察は迂闊にも、その単語が読めないゆえに、出版を許している。「反体制」という言葉も、この国には存在しないので、まさかと思っている。「抵抗」という言葉も、文中には出てこないので、読者には、薄っすらと気づくように書いた。
この雑誌が、元首の目にとまった時から、カタストロフが始まる。「孤高の豚」にしか読めない単語・分からない思想で、書かれている。
三人は、逮捕され、奇妙な取り調べを受け、三ヶ月間の勾留の末、終身刑になる。
民衆は、いつしか雑誌の事を一切忘れ。冒頭の一文が繰り返され、物語は終る。
と言う短編を数人に読んでもらったが、理解されなかったのか、不評でした。
ゲラは破棄し、データも削除しました。固有名詞は、「孤高の豚」一つしか出てきません。主人公たちたち三人も名前を持ちません。仮に、A B Cと呼ばれます。
了