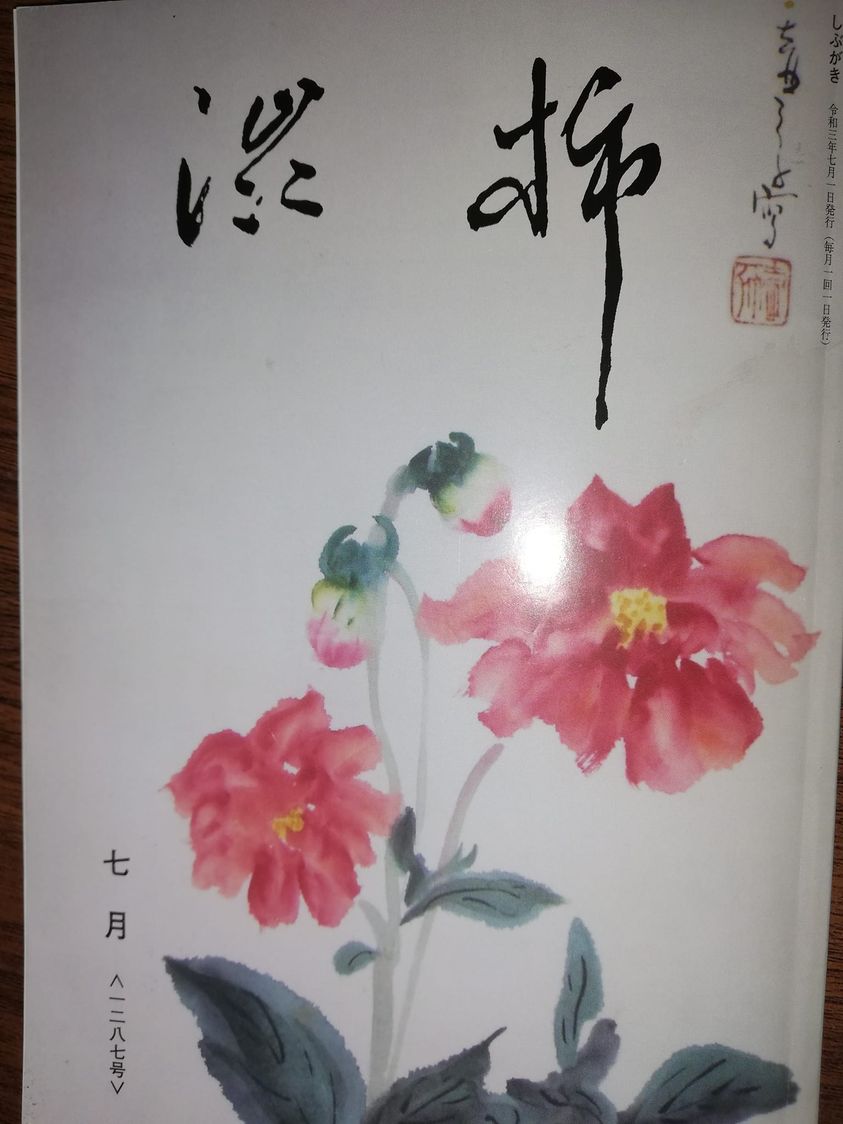桝田武宗
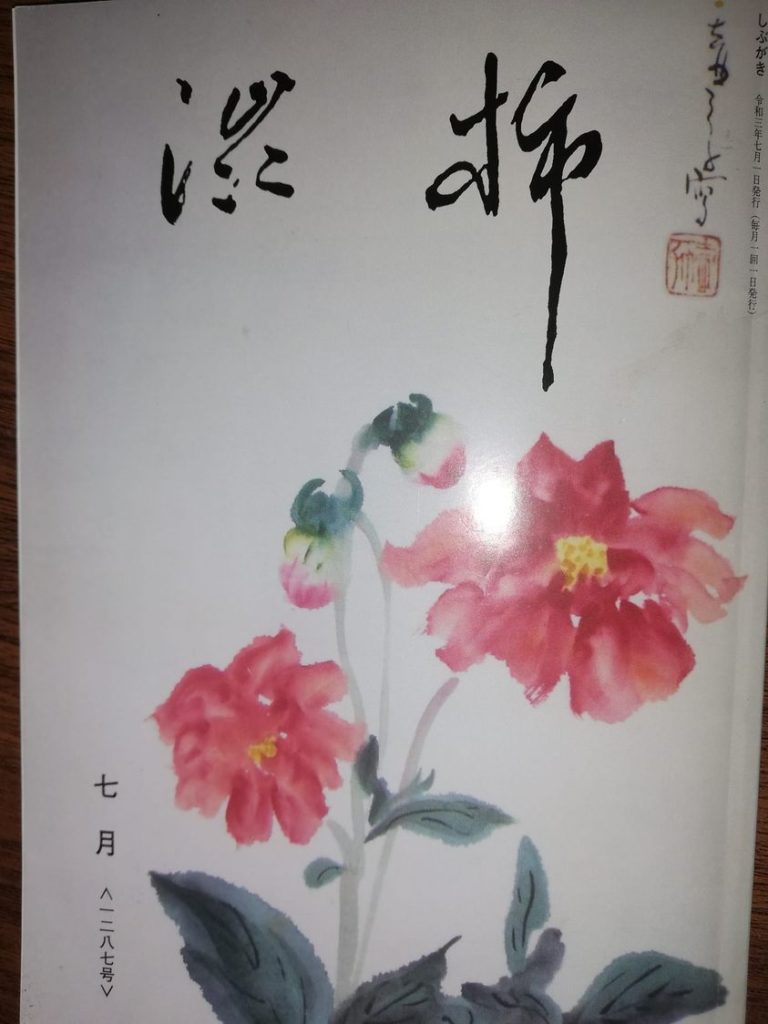
近代俳句の始祖である正岡子規は、「俳句は写生であり、実景・実物の静止している状態を捉えて十七文字の形態に固定するのが基本である」と定義しました。
子規が、「俳句革新運動」を開始した明治二十年代は、日本の西洋化・近代化が急速に推し進められていた時期で、その風潮は芸術の分野にまで広がっていました。そういう状況にあって子規は古い発想や表現が類型化していた俳諧を否定して芸術の域まで高めるために、「俳句」という言葉を創って俳句革新運動の旗印にしたと言って良いでしょう。
子規の俳句革新運動の理論的背景になった「自然主義芸術論」というのはイタリアの風景画家、アントニオ・フォンタネージュによって伝えられました。経緯は、フォンタネージュの弟子であった西洋画家・浅井忠から中村不折が「自然主義」というフランスで起こった芸術理論について聞き、それを子規に示唆したとされています。
フォンタネージュは、伊藤博文が推進して明治九年に創設した日本初の官立美術学校・工部美術学校の教師としてイタリアから招聘されています。フォンタネージュは、フランスの自然主義画家の代表であるカミーユ・コローやジャン=フランソワ・ミレーのバルビゾン派と言われた画家との交流があり、彼自身も自然主義画家だったのです。
自然主義芸術というのは、エミール・ゾラが提唱した文学の世界で起こった芸術運動でした。「ルーガン・マッカール叢書」(全二十巻)に収められている「居酒屋」「ナナ」がその代表作です。ゾラの「自然主義文学」というのは、自然の事実を観察して真実を描くことを目的としたもので、あらゆる美化を否定するものです。更に言えば、ダーウィンの「進化論」やクロード・ベルナールの「実験医学序説」を下敷きにして、小説の中に自然とその法則の作用や遺伝と社会環境の因果関係をベースに人間を描こうというものでした。小説家では、ゾラの他に「女の一生」のモーパッサンや「ボヴァリー夫人」のフローベルがあげられます。
絵画の世界では、先に書いたコローやミレーのように新古典主義やロマン主義に見られるような神話や物語の背景としての風景ではなく、「フォンテーヌブローの森」(コロー)や「晩鐘」「種まく人」(ミレー)のような貧しく慎ましく生きる農民の姿や身近にあるありふれた風景を題材とした作品が、「自然主義絵画」の代表作品になっています。
この自然主義派の風景画の様式が、フランスに於ける風景画の始まりとなりました。つまり、自然主義は、それまでの絵画の在り方を否定する形で出現したものだったのです。
子規の言う、「写生・実写」というのはまさに自然主義的発想です。コローやミレーの風景画を見れば、一目瞭然です。
しかし私は、絵画のような二次元に於ける表現と、文章によって景を表現する芸術には解離があると思います。
また、フランスで起こった自然主義芸術運動には、第二帝政下のフランスという社会学的背景がありました。「写実主義」も「自然主義」も、所謂「リアリズム芸術論」は、社会の有り様が深く関わっています。それが、ルネッサンス以降のヨーロッパの芸術運動の核だったのです。子規の写生論では、技術的な面が主要なものになっていて、社会学的部分が欠落していました。
正岡子規が、自然をあるがままに再現するとした自然主義の芸術理論を俳句に取り入れたところには、古い俳諧の「月並み俳句」を否定すると共に俳句を芸術の域まで持ち上げようとする国家の要請、あるいは時代の要請に応えようとする子規の姿が窺えるように思うのは私だけでしょうか。
この近代俳句の始祖である子規は芭蕉と蕪村の句を「理想的美」「複雑的美」「精密的美」というように様々な美の観点から比較・分析して蕪村の句を芭蕉の句よりも優れているとしました。それによって、およそ百年間認められなかった俳人蕪村を世に送り出すことになったのです。
*漱石も俳句を投稿していた俳誌「渋柿」令和3年8月〈1288号〉より、転載。