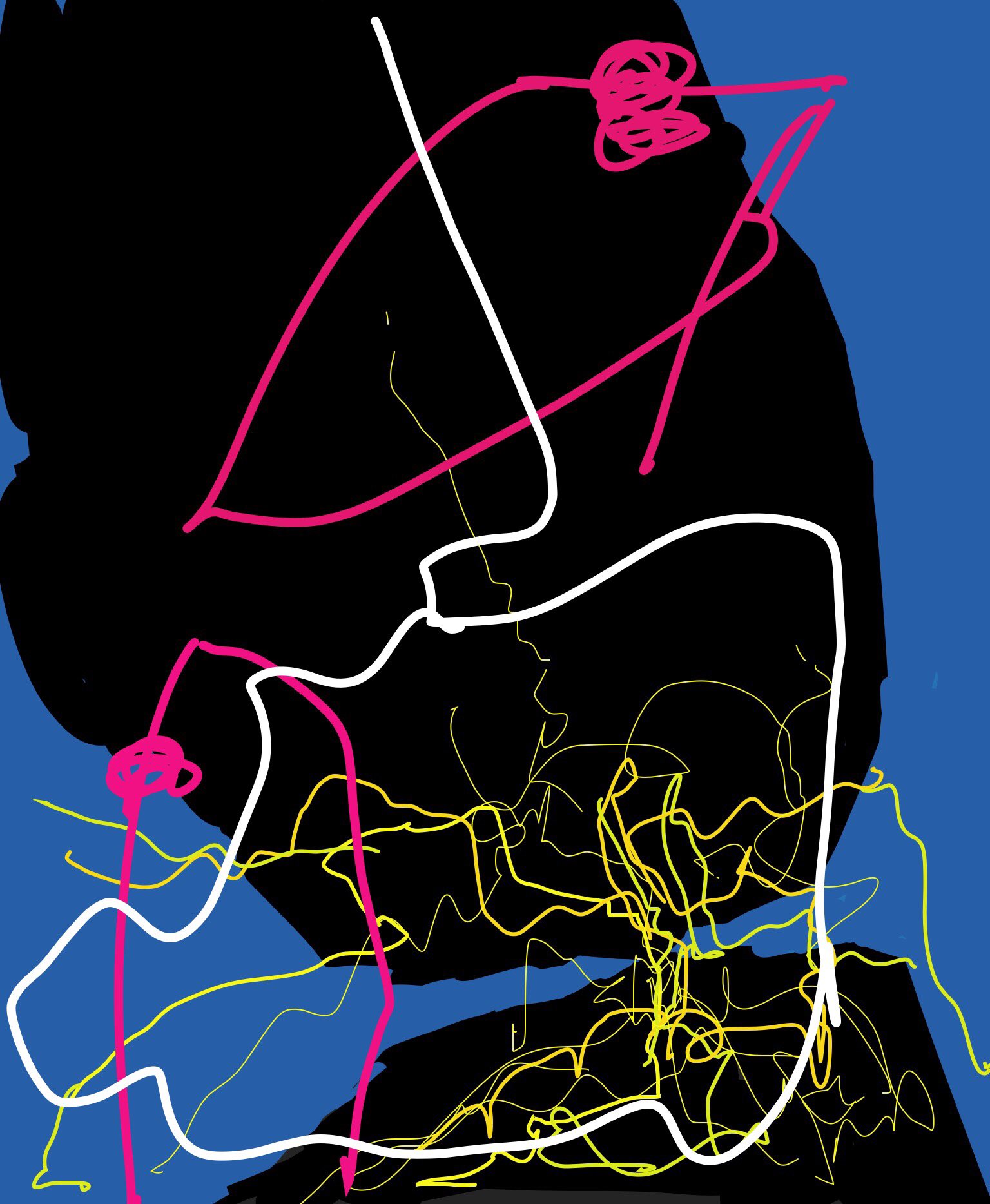山本幸生
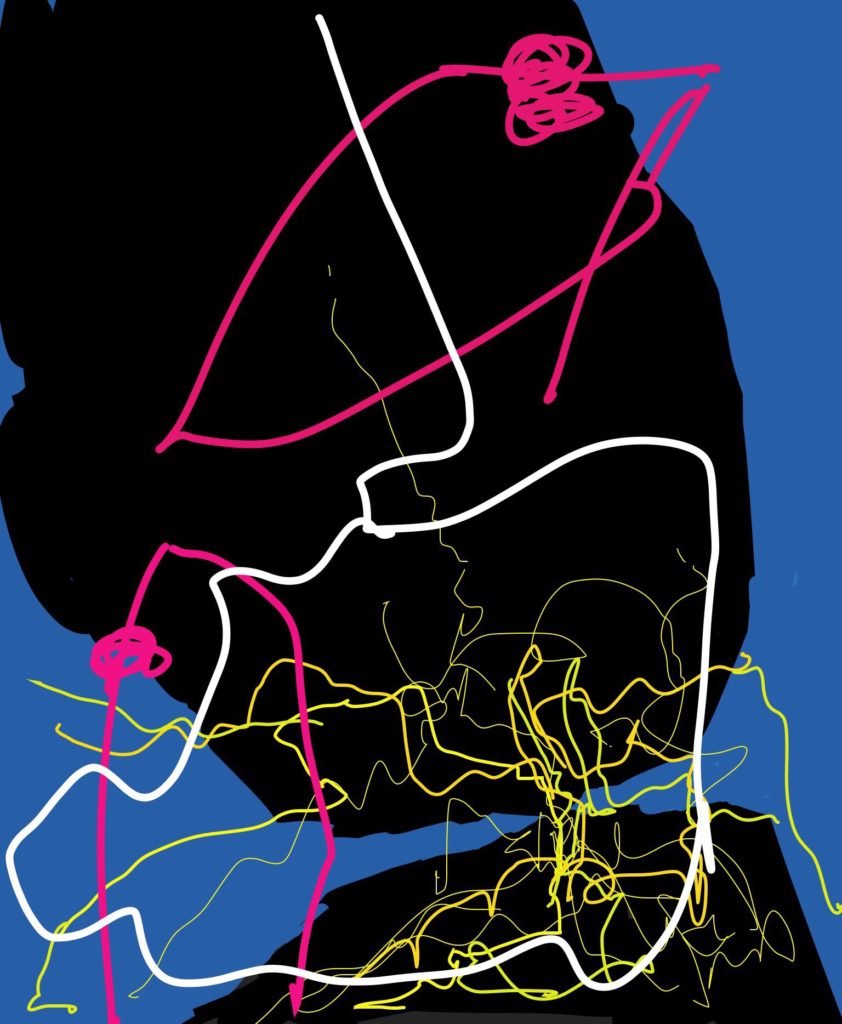
私の場合、「インド系統」後において、イスラム系やユダヤ思想関連、更には日本思想などもいくつか通過してから、ようやく「西洋哲学」というのに本格的に取り組むようになり現在に至る、ということだが、ここはあくまで「東洋哲学」というのがテーマなので、その後の「西洋もの」遍歴については割愛させていただくことにする。
ただ、一点だけ言っておくと、もし私が「前段階」において中国やインド系の思想を通り抜けていなければ、おそらく「西洋哲学」に本当の関心を持つこともなかっただろう、ということだ。実際、学生時代あたりにおいても、当然いくつかの「西洋哲学」には接していたわけであるけれども、その時はどうもぴったりこなかったというか、当時の「自分の問題」とはちょっとモノ的にズレたもの、という認識だったのであり、そのままの延長で進んでいくならば、再び「西洋哲学」と真に出会うことがあったかのかどうかわからない。
先にもどこかで書いたが、私自身の問題というのは自己および世界の「絶対的」な不確定性ということであったわけであり、いわゆる「西洋」諸思想が私の問題に対する「答え」を提供してくれる、というイメージはあまり持ち得なかった。私の目から見ると、それはあまりにも「安定的」であり、「静的」であり、問題に対する答えというよりは、すでに根本的な問題が解決された後において「落ち着いて」積み上げていくもの、という印象だったからであり、そしてその印象というのは今も基本的には変わっていない。
プラトンやアリストテレス、デカルト等々はもちろんのこと、「万物は流転する」のヘラクレイトスやニーチェ、ドゥルーズでさえ、私からすればあまりにも「静的」であり、「安定し過ぎて」いる。より正確に言うならばそれらには「底割れ感」というものがなく、どんなアクロバティックな論においても常にその奥底にはある種の分厚い「岩盤」が感じられる。
そのこと自体を批判する気は全然ないし、それがまさに「西洋思想」の魅力でもあるわけだが、「絶対的不確定性」としての「底割れ感」を回収するためには、少なくとも私に関して言えば「インド系」等々の「東洋」というものが必要であったわけであり、それらが概ね意識化できた段階で初めて「西洋」というものが魅力的に浮上してきた、ということであったのだ。
この東洋思想の「底割れ感」というものについては次回(最終回)で詳しく語っていきたいと思う。
主催Facebookグループ「哲学、文学、アートその他について議論する会」