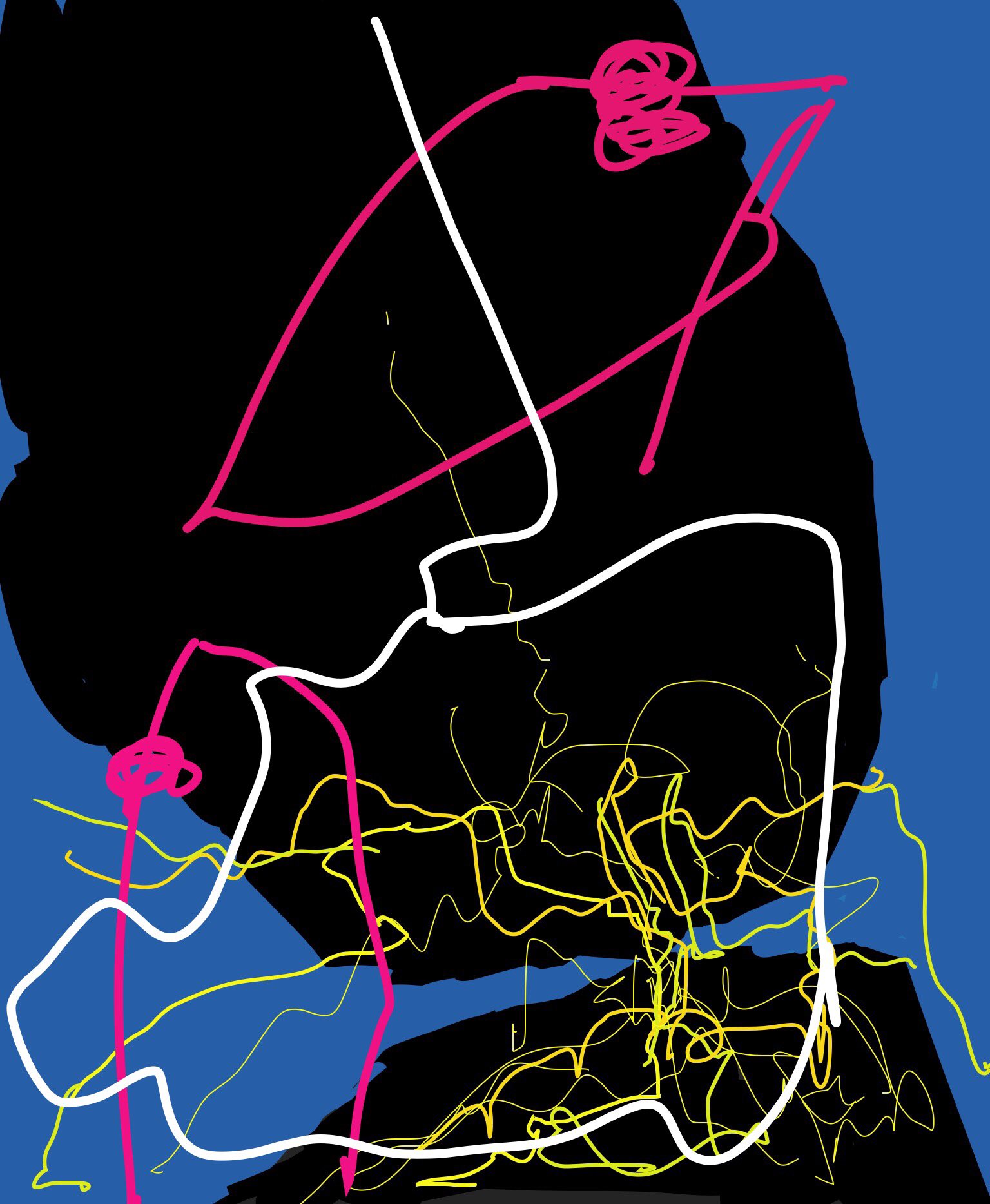山本幸生
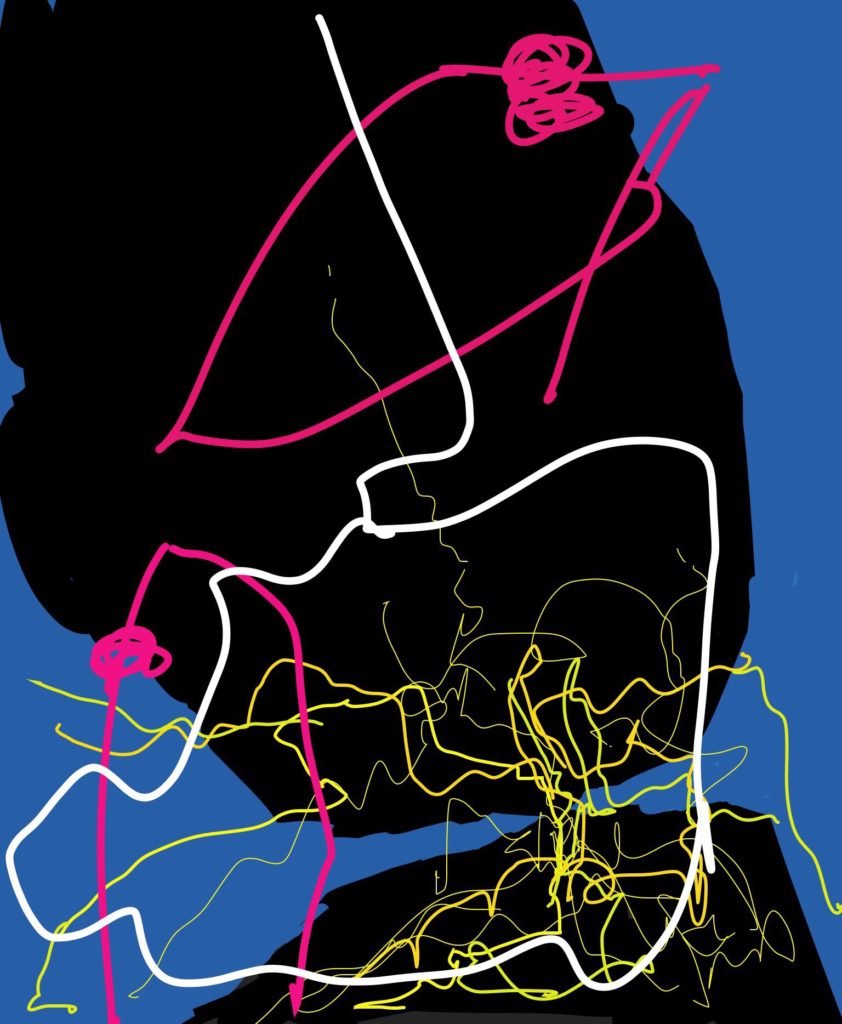
前回触れた、その「最後のピース」であったところの「フランス(特に哲学)」というものについていうと、まず最初の「出会い」はドゥルーズという哲学者の本だった。たぶん一番はじめに読んだのは「アンチ・オイディプス」という(結構有名な)本であったと思うが、正直、内容はよくわからなかったものの、そのスタイルが、それまで持っていた「哲学書」というもののイメージを完全に覆すものであったことから大いに興味を持ったのだった。
当初はドゥルーズだけを読んでいたが、そのうち彼周辺のフランス現代思想全般に広がり、更にはそれを契機にフランス語やフランス文化一般にも興味が拡大して、かつての「無関心と嫌悪」から、今や国単位で言うとフランスが「西洋」の中では一番興味のある国、ということになったのだった(この点は現在でも変わっていない)。
「フランス現代思想」についての個別の論評はまた別な機会に譲るとして、大雑把に言うと、一番面白いと思ったのは先のドゥルーズ、それとアルチュセール、レヴィナスあたり、中くらいがラカン、メルロ=ポンティ、バルト等、正直つまらないと思ったのが、フーコー、デリダ、レヴィ・ストロース、といったところ。まあこの順序にはかなりの異論があるだろうが笑(これらの面々は現代フランス哲学においては皆「大御所」級の人たちであるが、フランス思想に馴染みのない人は、単にそういう連中がいた、ということくらいで流してもらえばよいかと)。
いずれにせよ、このフランス思想との出会いによって、哲学への興味というのが完全に覚醒し、その後フランスのみならずあらゆる分野、時代の哲学に関する文献を読んでいくことになる。位置付け的には、それまでの「基礎工事」が終わって、ようやく「建物の建設」段階に入った、というところか。
このことからもわかるように、「西洋」というのは基本的にまず「建物」でなければならない、というのが私のイメージである。その「基盤」を問うことはあるが、その問いは必ず「終わる時」がなければならず、その終わったところから何物かが「建設」されないと、それは「意味がない」というのが西洋的な感覚である。一方「東洋」では、その「基盤」というものについての堂々巡りな問いというもの自体に価値がある、というような感覚があるように思う。
基盤、というのはいわば「宇宙そのもの」であるが、東洋世界が、ほとんどこの「宇宙そのものの構造」にしか興味がないのに対し、西洋ではその構造を何らかの形で決定したのちに何を建設するか、というのが重要、ということである(もっとも東アジア世界においては、抽象的な宇宙というよりはむしろ「人間関係」の宇宙、といった感じかもしれない) 。
次回からはちょっと「国単位」で様々な「西洋」の様子を見ていきたいと思います。
主宰Facebookグループ「哲学、文学、アートその他について議論する会」