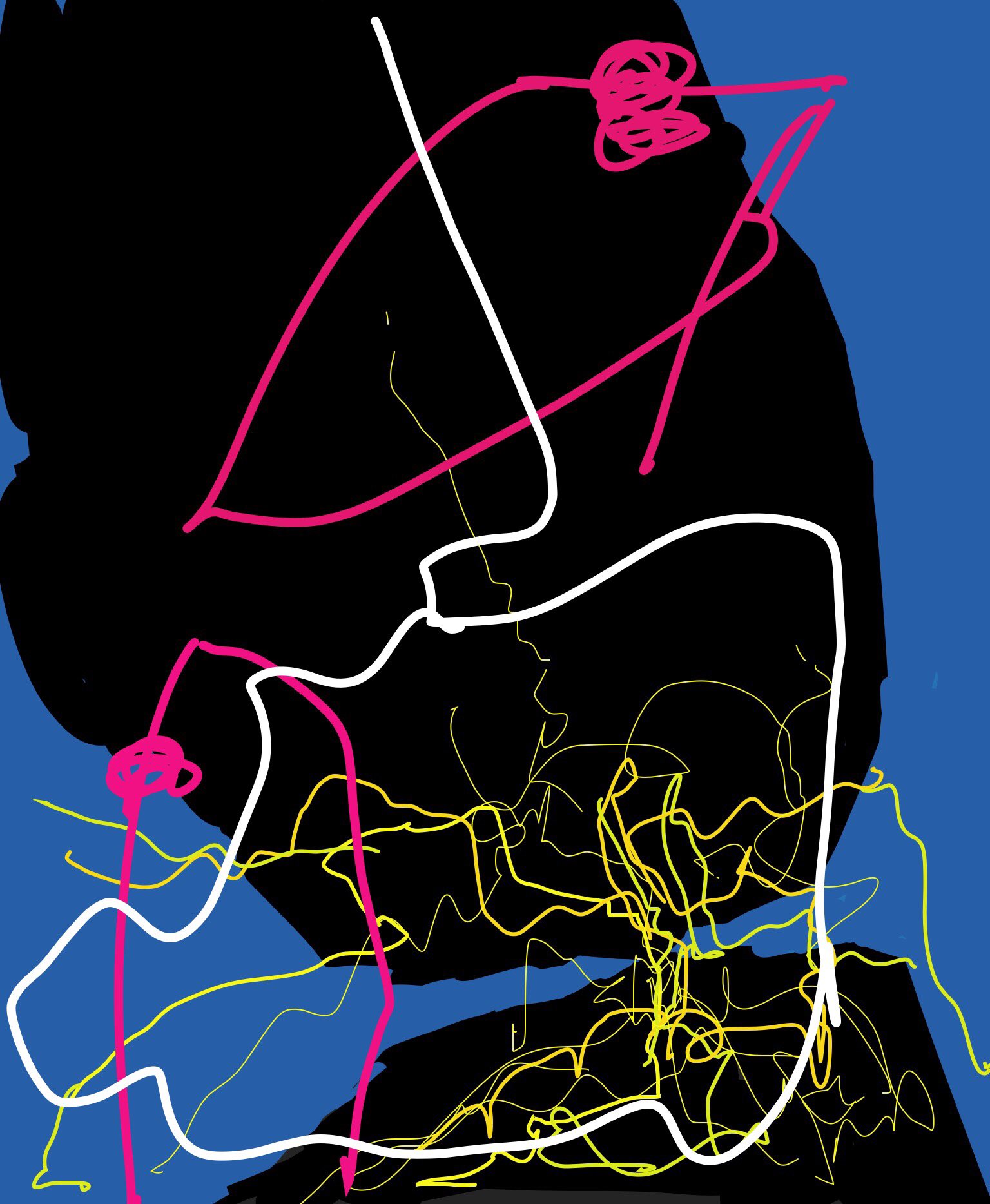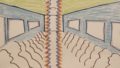山本幸生
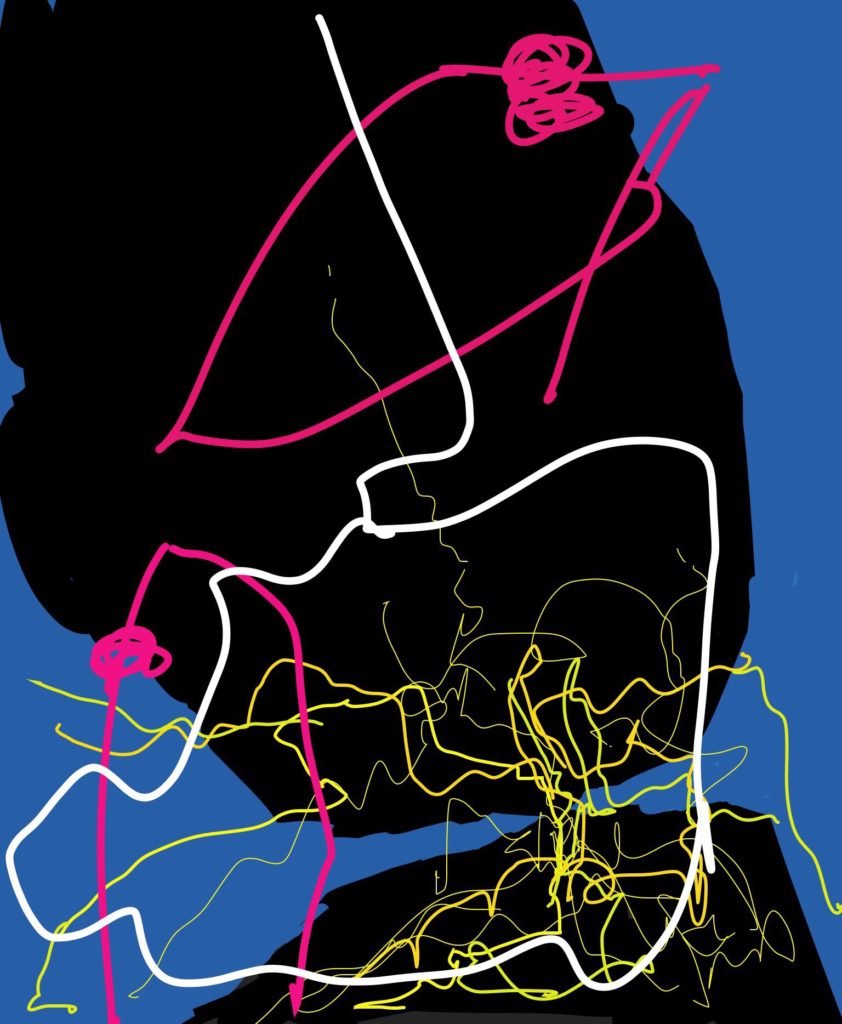
実は、いわゆる「西洋哲学」の本を本格的に読み始める以前、私は中国思想にかなりハマっていた。諸子百家と言われる思想家たちのうち、岩波あたりで出ているものはほとんど読んだし、岩波になかった「墨子」などはハードカバーの単行本などを買って読んだ(これは「兼愛」ということで結構期待していたが、内容はかなりお粗末でがっかりしたが)。
中でも気に入って繰り返し読んだのが「荘子」であり、この本が事実上私にとっての「最初の思想書」となったのだった(その本は今でも本棚に飾ってあるが、もう二度と再読することはないであろう。。)。おそらく当時は荘子特有の「抽象思考」そして自己のみに基盤を置く「絶対個人主義」というものに魅力を感じたのだろうと思うが、本当に面白いのは4巻本の最初の2巻くらいで、後の2巻は繰り返しも多く、実際、それらは荘子の直筆?ではなく、後に弟子たちが編纂したもの、ということらしい。
その後、「韓非子」なども、気持ちのいいほど歯切れの良い専制君主肯定思想で結構面白く読んだが、やがて中国思想そのものからは完全に離れてしまった。その理由というのが、先の稿で述べた中国思想の根本的な「処世学的」性質であった、と今にして思うわけである。
かなり浮世離れした抽象的な部分も多い「荘子」ですら、究極のところは「世の中において周囲の人間に惑わされずに生きていく」ための思考法、というのがその根幹なのであって、それがある種の「形而上学」によって基礎付けられている、というのが他の思想とは違った魅力ではあるのだが、形而上学はあくまで「だし」あるいは「イメージ」にすぎず、それ自身として知的に深められることはないし、おそらくそうするつもりもない。
このことが中国思想の「限界」だ、と言えるのかどうかわからないが(「世間的な知こそ本当の知である」という立場もあり得るだろうから)、少なくとも私に関して言えば、それは「物足りなさ」以外の何物でもなかった、ということなのである。
すなわち、そこにおいては「存在が存在として」問われているわけではなく、あくまで世間的な「心の持ちよう」についての「知」が語られているのであって、それはギリギリのところで私が求めているものとは違っていた、ということだろうと思う。(中国にも「宇宙論」のようなものもあるのは事実だが、それが中国思想の根幹と本質的に結びついている、という感じはしない。中国文化はあくまで「人間」あるいは「形而下」主体の文化であり、形而上は何かに必要な時に適宜引用されるに過ぎない、というのが私の印象である)
ただ、そうしたことはあくまで一度、中国思想、あるいは局限すれば「荘子」を通過して初めて気づくことができたものであり、一つの「段階」としての「中国体験」というのは私にとって非常に有意義なものであったと考えている。
その意味で中国に対しては、いまだに、文化的に「恩義がある」国、という形で尊敬の念を持っております(むろん今の中共にではなく、古代の思想に、ということだが)。
https://www.facebook.com/groups/2442951352610339/?ref=share_group_link