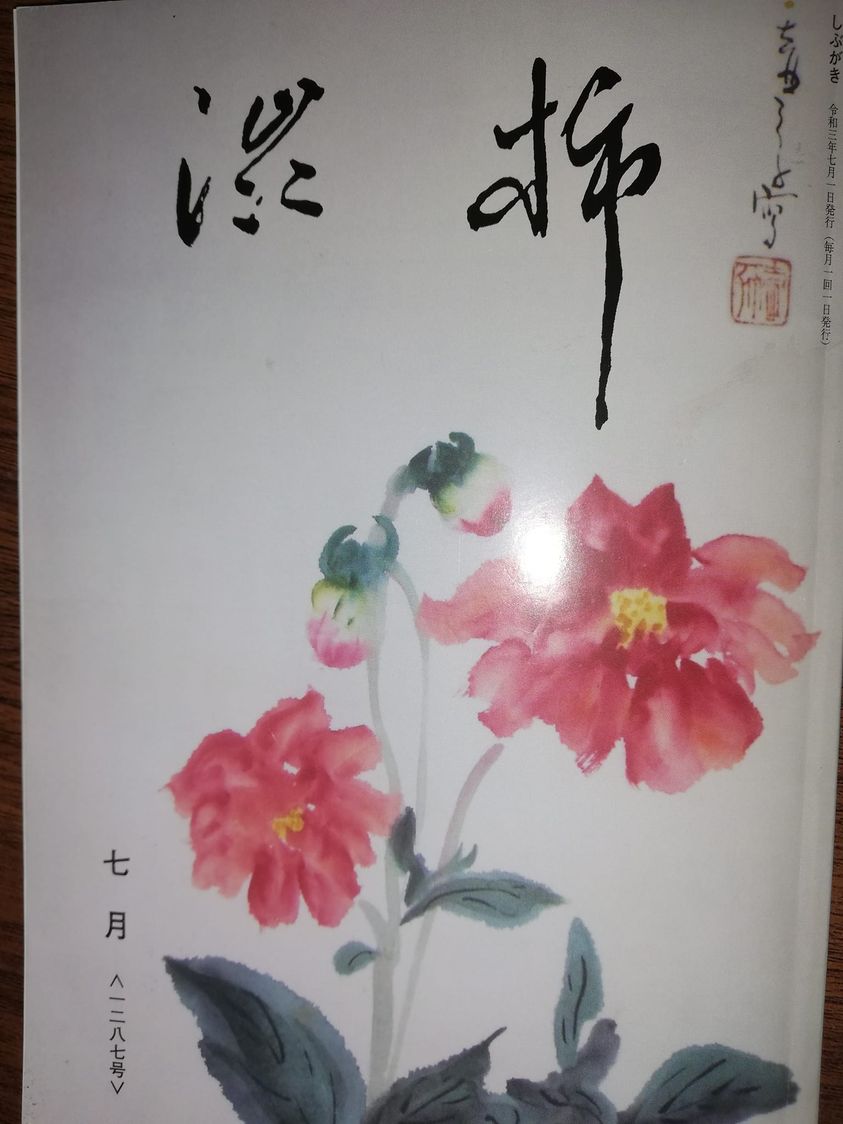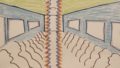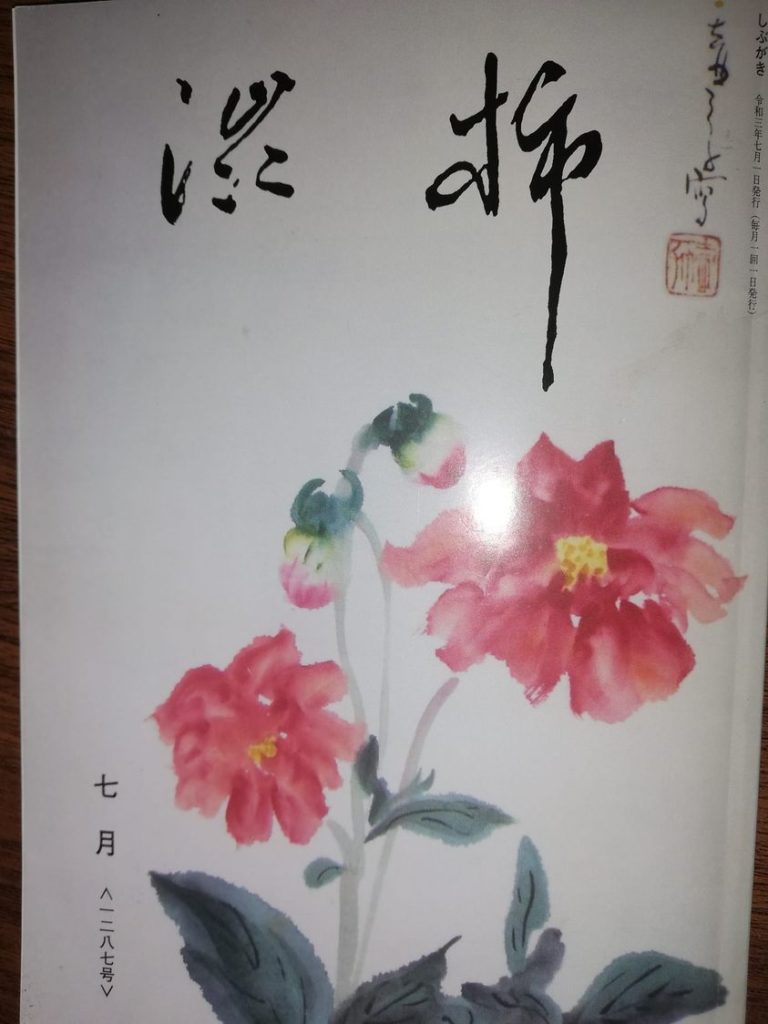
桝田武宗
俳句は、大前提として季語を詠み込むことになっています。季語は、暦と深く関わっているものであり暦は時を表します。また俳句は、時の流れの瞬間を捉えて景を詠むというもう一つの前提があります。私が、ここで書く時(時間)とは、「内在的時間」とか、「詩的律動と音数律による時間性」のことではなく句に詠み込まれた純粋な時間を指すものです。
今回は、芭蕉が生きた江戸時代初期から蕪村が蕉風を唱えた江戸時代中期に於いて時間がどのように認識されていたのかということを書くことにします。
この時間認識をうまく表しているのが芭蕉の「奥の細道」の冒頭文「月日は百代の過客にして行き交ふ年もまた旅人なり」です。これは李白の、「春夜宴桃李園序」(春の夜桃李園に宴するの序)を芭蕉が引用して書いた一文です。この一文の解釈について哲学者であり、梅原日本学の創始者である梅原猛は次のように言っています。「日や月は目に見えるが年は目に見えない。しかし、厳然と存在している。年には春夏秋冬という生死がある。目に見える天体(日月)も永遠に生死を繰り返す旅人であり、目に見えない年という宇宙の運行そのものまた生死を繰り返す旅人である」。“年が宇宙の運行そのものである”と述べているところには流石梅原猛だと言えますが、この解釈は誤りです。それは李白の、「春夜宴桃李園序」の内容「夫れ天地は万物の逆旅にして光陰は百代の過客なり」を読めば明らかになります。
この一文の解釈は、「そもそも天地は、万物を受け入れる宿であり時の流れは永遠の旅人である」ということです。「過客」は、「通り過ぎて行き永遠に旅を続ける人」という意味で、「行き交ふ年という旅人」は、「再び巡り来る人」という意味なのです。
芭蕉のような名文家が、「過客」と「旅人」の違いを間違えるとは思えません。
「パタゴニア」「ソングライン」「どうして僕はこんなところに」などの著作を残したブルース・チャトウィンというイギリスの紀行作家がいました。その旅の達人チャトウィンも、
「旅人というのは、一つの社会に属している者で旅に出かけても必ず自分が所属している社会に戻って来る」と言っています。
余談になりますが、チャトウィンは旅の途中で亡くなったのですが、彼の遺品の中に英訳された「奥の細道」があったそうです。因みに、「奥の細道」の英訳本は三種類あって、その英訳されたタイトルは、「A Haiku Journey」と「The narrow road of Oku」と「Basho’s narrow road」というものです。余談はさておき、「奥の細道」の解釈から芭蕉の時代に於いて「不可逆の時間」と「循環する時間」という概念があったことが推察されます。
では、時刻についての認識はどのようなものであったかというと、江戸時代を通して時刻は不定時法が使用されていました。不定時法というのは夜明けと日没を基準にして昼と夜に分け、それを六等分してその長さを一刻としていました。従って、一日の中でも昼と夜の一刻の長さは異なり、季節によっても異なっていたのです。
現在は、「常用時」を使っていますので午前零時を一日の始まりとしています。しかし、江戸時代は「日の出」を一日の始まりとしていました。「日の出」「日没」そして、「正午」という時刻を認識して生活していたのです。
一日の始まりは使っている暦によって違っていて、「ユダヤ歴」や「イスラム歴」では「日没」を一日の始まりとしています。日本においても神社では、一日の始まりを「日没」としています。神社の祭礼が、夕方の宵宮から始まって夜間のうちに終えるようになっているのはそのためなのです。江戸時代に於いて時間は、共同体単位のものであり、共同体を支配する者が管理していました。個人の時間の概念は明治時代以降になって確立されます。
俳句は、季語を使わなくてはならないという決まりがありますから暦や時間は切っても切れない関係にあるのです。
(※以上、漱石も寄稿していた俳誌「渋柿」令和3年7月(1287号)より転載。)