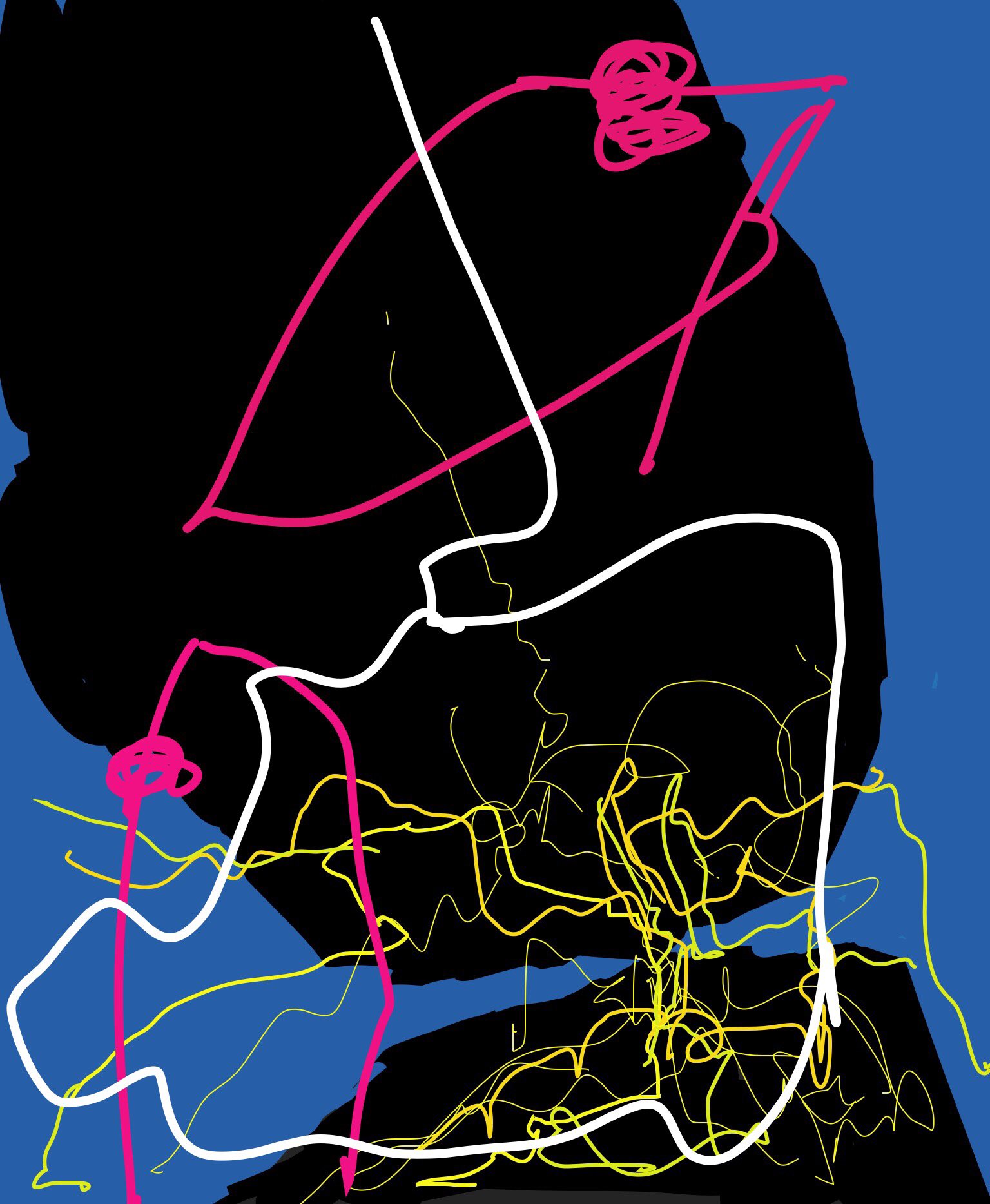山本幸生
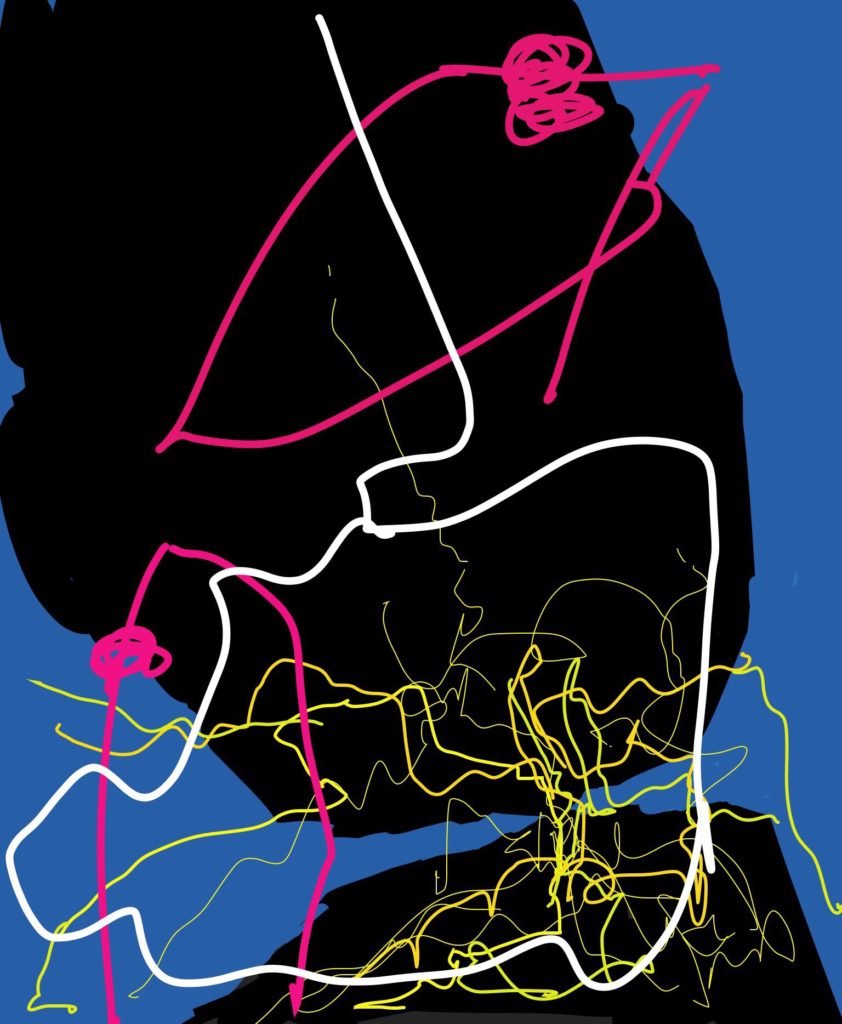
あまりにもテーマが大きすぎるので、とりあえず私自身と「西洋」というものとの個人的な関わり、というあたりから語り始めてみたい。
私の大学での専門は数学だが、当時の私は西洋という点に関していうと、ごく素朴な、さらに言えば、かなり幼稚なレベルの「西洋主義者」だった。
宗教といえばもちろんキリスト教のこと、音楽もクラシックオンリー(具体的にはモーツァルトオンリー)で、専門の数学を始め、あらゆる分野において頭の中は「カタカナの名前」で満ち溢れていて、それ以外の(ただの「傍流」ではない)世界があり得るということを想像すらしていなかったし、まして「日本のもの」などは歯牙にもかけなかった(文学においては、漱石など好きな日本人作家はいたが、一番耽溺したのはドストエフスキーやカフカであった。もっとも果たしてロシアも「西洋」に入れるべきかどうかは今にして思えば微妙なところであるが)。
ただ、当時の私の関心はあくまで数学に集中していたわけなので、その世界の中にいる限りは、「西洋の単純な延長」にいることに特に不都合はなかったし、おそらくそのまま数学を続けていれば、今でもその時の路線の先にいただろうと思う(当時、哲学というものについてもそこそこ興味は持っていたが、あくまで単に趣味的な関心ということでしかなかったし、読書にしてもカントやギリシャものの主要どころをいくつかざっと読んだに過ぎない)
しかし、その後もろもろあって数学からは足を洗う? ことになり、その段階から「西洋」というものとの「単純で幼稚な」関係にも微妙なズレが出始めてきた、ということになる。
すなわち、自分自身が「底割れ」したことによる「東洋への接近」ということになるわけだが、その間も「西洋」からは完全に離れてしまったというわけではなく、「政治」というものとの絡みで、学生時代までには全く興味がなかった「イギリス」というものと出会い、しばしその思考構造に魅了される時期が続く。
そしてそれがようやく一巡したころに出会ったのが「フランス思想」というものだった。ここで(少なくとも私にとって)重要だったのは、「西洋」というものの中でも「フランス」については、かの「単純で幼稚な西洋主義者」時代においてすら、その魅力というのが全く理解できなかっただけでなく、ほとんど嫌悪のようなものすら感じていたのだが、その段階でようやく「フランス」に出会うことにより、私の中で「西洋」というものの最後のピースが完全にはまった、という感覚を持ったことだ。
つまり、まとめると私の「西洋遍歴」というのは、ドイツ・ロシア系の「深淵なる東」側から始まり、やや淡白な「アングロ系」を経て、最後に「フランス」に至る、という経緯であり、これらの魅力と特徴(あるいは「欠陥」)が全て概ね把握できたことにより、自分の中では「西洋全体がカバーされた」という感覚が持てるようになった、ということである(古代中世西洋、についてはもともとある程度「わかって」いたし、スペイン・イタリア等「西洋の他の国々」の魅力も知っていた。アメリカについては戦後日本人としての単純な「アメリカ文化刷り込み」によってやはりごく普通に「わかって」いた)。
むろんこれはそれらの地域における個々の「思想・文化内容」について全て理解したということではなく、あくまでそれら「全体」としてのイメージが自分の中に形成された、ということであるが、その「大枠のイメージ」から見ると「個々の思想や事象」というのも結構よく把握できる部分があり、私にとってはそれが最も重要なことであったのだ(というのも私が哲学に興味があるのは、常にそれを自分の問題に適用する、という観点からであり、いまだかつて「哲学内容の専門家」になりたいと思ったことは一度もない)。 (次回に続く)
主催Facebookグループ「哲学、文学、アートその他について議論する会」