柴﨑政夫
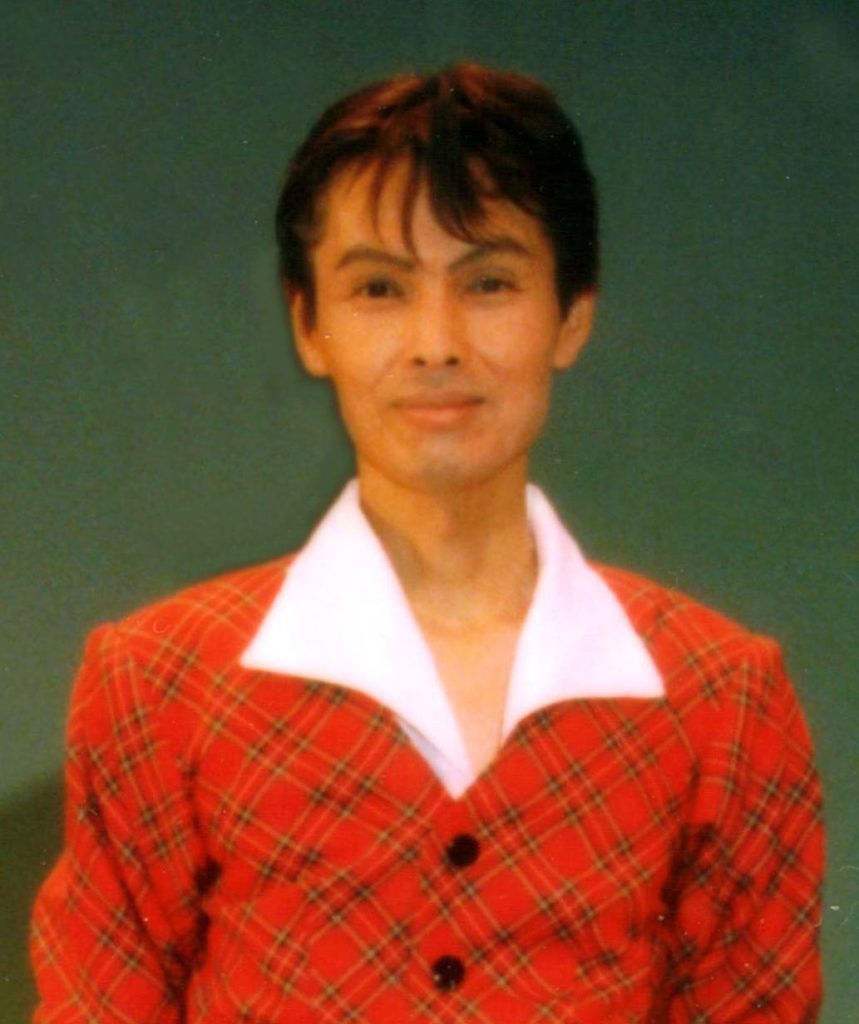
後になって気づいたことだが、半年ごとの養成所のカリキュラム計画と発表については、後になって、娘がロシア留学した際に出題されたものと極似する内容だった。
歌唱発表、抜粋場面の演技発表、肉体表現、論文発表。そして最後に総合作品としての公演体験。
舞踊に置き換えると、基本練習、ソロ、コンテンポラリ-ダンス及びマイム、論文提出、公演演目、という具合である。
奇妙なことに、私は誰かと合同での歌唱、黒子役での場面転換役、肉体表現の際の伴奏的朗読役、論文だけ自己発表。公演体験では1人3役の早変わり。…単独表現なし。
つまり、周囲の思惑によって、かなり使いまわしできる便利な人材だったようである。
初っぱなは名作の有名シ-ン抜粋からなのだったが、「カモメ」「ロミオとジュリエット」「私のかわいそうなマラ-ト」等々。
しかし、個性が外国向きの私に比べて、他はほとんどが日本的。
となると、自然と作品がやりくりされて移行する。→日本的演出を加味。
比べるまでもなく、私の得意は新劇従来からの外人若手風の役柄。
←わかりきってるから、顔を隠して、何役でも動き回させて、一方的な使い回しというやり方。
さらにメイクを加えれば、初老のコメディ風軽妙なドラマでの通りすがりの人物描写。
これが結構できるから、まあ、並以上のできばえだったのだろう。
しかし、当時は、朝の連続ドラマの主役探し(女子)をNHKとTBSが競ってた時代。
業界陣は男の人材には興味なし。←ほとんどが貧乏人で肉体派ばかり。
近年、暴露記事が、当時の商業演劇で新人男性役たちが何してたかを遠慮なく書いている。
新人男に頭髪をコテコテに光らせ、意味なく笑顔を作り、着飾ってうろうろさせた。
となれば、演技以前に見かけが大事。顔はほぼ横並びだから、背丈で判断。
いつの間にか、音楽業界やモデル業界の人間が、横から自然参加する状況に。
彼らは1本契約が目当てだから、ほとんどが無給でうろうろ。→当てればでかい。というわけ。←その前に「頭髪衣装込み」で指導料等が自腹のプロダクション出身ばかり。
これが、つい最近まで続いてたわけだ。
17、18~25才までが勝負の時代。
ここにつけ込んだのが15才から丸抱えする会社。
男女問わず、補助的参加から体験実習をかねて、スタジオの雰囲気を学ばせれば、自然淘汰。
子どもタレントから青春時代の過渡期に必要な脇役たちを集めることで急成長できる会社が出てきた。
特に、はじめは無料体験レッスン。というのが売りだった。
ところが、私だけは翻訳劇の新劇路線。役柄演技に夢中。
研究所側は周囲とバランスを取るため、次々、アレンジしながら掛け合わせ的条件を重ねて使おうとしてゆく。
陰で誰かを支える歌だけでなく、身体表現もバックに回され、、琵琶法師の弾き語りテ-プを聴いて、再現。
舞台公演で朗唱。←不可能に近いことを「お前ならできる」で引き受ける。
音大の入試に聴音を記譜する試験があるが、その場合、絶対音感が必要とされる。
私は子ども時代にその訓練受けてないのだが、この時、音符にない日本の弾き語りを聴いて、骨伝導を使って、共鳴することを身体が覚え、そこから、音階を作って、自分なりに再現できることを体得した。
幼児期に民謡、和楽器等の聞き比べが聴力を育てたせいであろうか。
発声は西洋音階の訓練しかなかったのだが、演歌歌手たち同様に、曲調のずれを感じ取ることができた。
そのまま、家元原作者の誰かに弟子入りすれば、人間国宝になれたかも知れぬが、当時、その系列の職業は様々な困難な状況にあった。
加えて、私が20代から50代まで我慢できたかといえば、「ノ-」だったであろう。
日本を代表する児童歌手やタレントたちは、ほとんどが、過去のテ-プを聞き、再現する手段で生き残っていた。
音大卒は譜面が読めるから業界では尊敬されていたが、売れるかどうかは、大衆の判断。それが当時の世情であった。
魅せるものがあるかどうかが鍵だった。
音程が確かでも、旋律内に揺れがないと想像力が生まれにくい。生硬な表現か、観客との間で少なからず影響を受け、揺れが発生する表現→複雑性と希少価値を有するかどうか。それがライブ表現の醍醐味であり、観客を魅了。そこに人々は奇跡を見いだしたのだった。
さて、当時はテレビ全盛時代。
一山当てようという若者がタレントスク-ルや個人事務所に殺到した時代。歌でいくか、お笑いでいくか、芝居でいくか。
そんな中、舞踊は少し敷居が高いジャンルだった。
もちろんバレエとモダンダンスのこと。
商業的なのは当て振り的な軽い扱いのものだけ。
当然、ミュ-ジカルなど海外物にはすぐには挑戦できない時代。
基礎訓練が導入されてない時代だったから。
私の周囲がねらっていたのが俗悪番組といわれたバラエティショ-番組出演。
他に怪獣特撮番組。青春学園ドラマ。刑事物番組。といった具合。
古典劇や近代劇への挑戦は、前時代の役者たちがいて、なかなか許してもらえぬ時代だった。
後に、これが新劇の崩壊を起こす要因となるわけだが、経験者たちからすれば「まだやれる」という感慨に浸りきっていたし、次世代育成など「自分を隠居させるのか」つまり、もってのほかという時代だった。
とはいうものの、15才から25才付近の人材だけは募集が必要。こうして、オ-ディションで週刊誌の話題づくり、興業へ。という流れができあがってゆく。

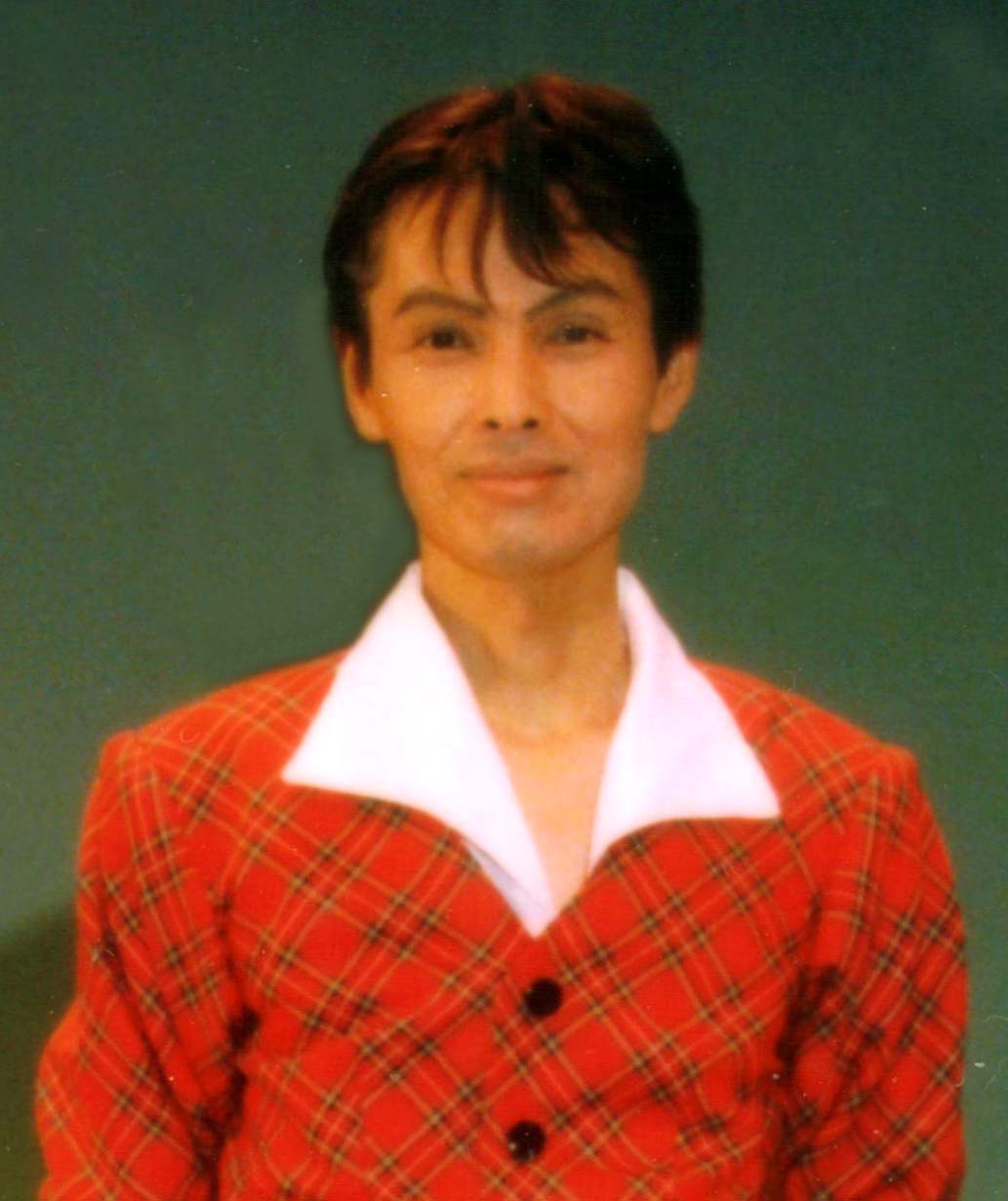


コメント