西之森涼子
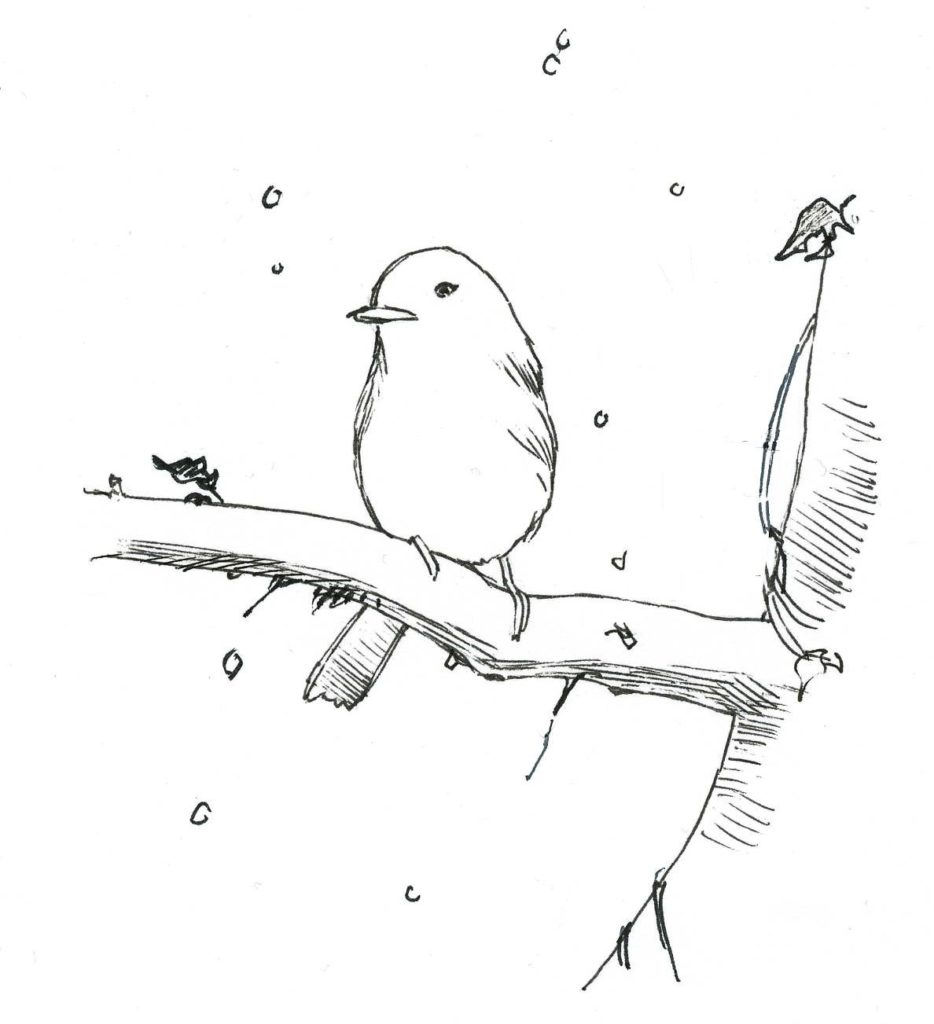
年が明けるととたんに寒さが増す。
そんな気がするのは、子供のころからなんとなく12月の慌ただしさが好きで寒さよりクリスマスや大晦日の楽しさに日々を過ごしてきたせいだろうか。
冬の匂い
冬と言われれば思い出す匂いは、年末に親戚で集まり杵でついた餅の匂い。
極寒の師走にワイワイ言いながら餅をつく父や叔父たち。
妹と私は笑顔の祖母やしっかり者の叔母たちに囲まれて、不器用ながらもつきたての餅に餡子を入れて大福などをつくるのが楽しんでいた。
冬の感触
川辺の氷。なぜ冷たいとわかっていても子供はわざわざ手袋を外して凍った水辺を触るのだろう。
冬の風景
最近私のお気に入りは朝、通勤経路の銀杏並木を通して見える真っ青な空。夏の青さとは違う冷たく透き通った空に白く乾いた銀杏の枝が映えてなんとも美しいのである。
冬の味
それはなんといってもすき焼に入った春菊。春菊は冬以外では食べたくないほど私の中であったかい冬の味覚になっている。
冬の音
雪がサラサラ降る音。
椿の葉に雪が降り積もり時々パサッと落ちる。
その音に気付いてみると真っ赤な花がそこだけ温かさを感じるほどに凛と咲いているのである。
こんな風に書き連ねると、まるで私が冬を心から愛しく思っているように誤解されそうである。が実は大の寒がり冷え性で最も苦手な季節なのである。
物心ついたころから冬になると「寒い。寒い」と一人で大騒ぎしてストーブから離れようとせず(また炬燵に潜り込み)家族から呆れられている子供だった。
そんな私が小学校低学年のときにある歌に出逢い、冬の音や匂いを感じられるようになった。
サトウハチロウ作詞の「もずが枯れ木で」である。
もずが枯れ木で
もずが枯れ木で鳴いている
おいらは藁をたたいてる
綿引車はおばあさん
コットン水車もまわってる
みんな去年とおなじだよ
けんども足りねえものがある
兄さの薪割る音がねえ
バッサリ薪割る音がねえ
兄さは満州さいっただよ
鉄砲で涙が光っただ
もずよ寒いと鳴くがいい
兄さはもっと寒いだろ
一見平和でゆったりした日本の原風景の中で、冬の音が沢山聞こえてくる。
もずの声、藁を叩く音、水車、そして足りない音は兄さの薪割る音。
いままであったのに失くした音の中に描かれた物語がある。
この冬の歌を知った時に、戦地の兄さを思う切々とした哀しさと涙がまだ幼い子供だった私の心にも深く染みてきた。
後に佐藤愛子著「血脈」を読みハチロウの人となりを知った。
傍若無人なふるまいとは裏腹に傷つきやすく繊細な面があったハチロウ。
この歌を作詞したときにはまだサトウハチロウは若く、戦争で家族を失うこともなかった。
しかし後の第2次世界大戦で弟二人を失くしている。
年が明けてしんしんと寒さを感じるこの季節、この歌を想い出すのである。

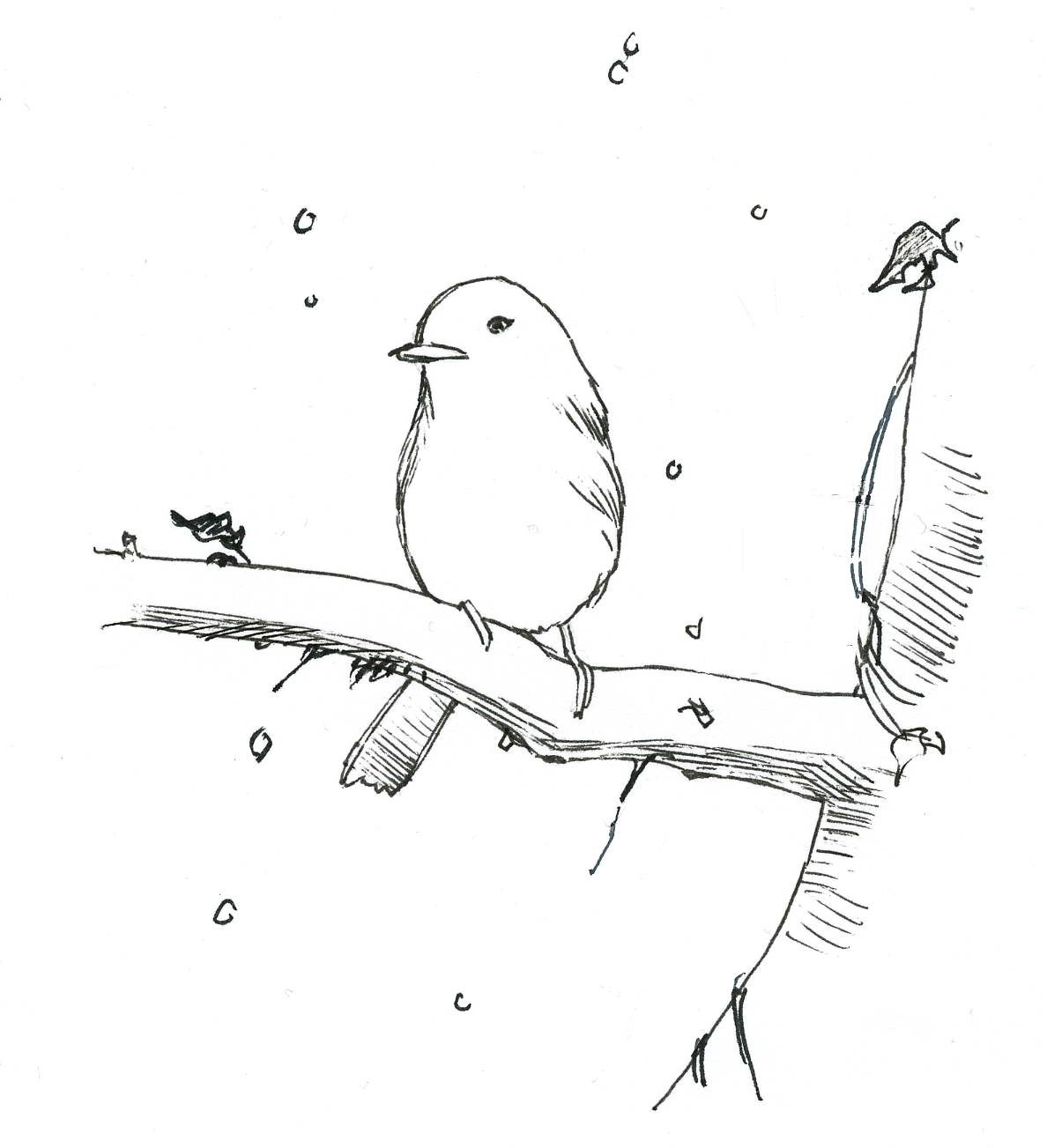


コメント